 Unit 03-B: 地方創生における少子化対策の在り方とは?
Unit 03-B: 地方創生における少子化対策の在り方とは?
札幌市立大学デザイン学部教授 原 俊彦
2014年、日本創成会議が「ストップ少子化・地方元気戦略」1)を発表、「人口再生産力に着目した市区町村別将来推計人口」とともに「人口移動が収束しない場合の全国市区町村別2040年推計人口に関する地図」で、「20~39歳女性」が50%以上減少する地域を明示し『地方消滅』の可能性を示唆したことはまだ記憶に新しい。これが契機となり『地方創生法』2)が施行され『まち・ひと・しごと創生本部』3)ができ、2015年現在、全国の市町村は「地方人口ビジョン」・「総合戦略」の策定に奔走している。
まず地方は「消滅する」かという問題。この推計では「純移動率(噂では純移動数)が変化しないと仮定」(高齢化や少子化の影響もあり純移動率(数)はすでに低下傾向にある)、「各市町村と都道府県や全国推計との整合性がない」(個々の市町村の値を合計すると都道府県や全国値から乖離する。統計学的には人口規模が大きい方が結果の信頼性も高く安定的なので、それにあわせ市町村間の補整が必要)など、専門家からみるとかなり乱暴な推計で、全般的に人口減少や高齢化率は社人研推計より過大となっている。さらに「消滅可能性」の基準を「20-39歳の女子人口が現状の50%未満になる」としているが、なぜ50%未満になると消滅可能性が高くなるのか、その根拠も曖昧なまま、基準に従えば東北・北海道は80%以上の自治体が「消滅」するとされた(全国49.8%)。この点について後に出版された『地方消滅』4)で改めて確認したところ1世代(推計期間と同じ30年で、この年齢の女子人口が50%(半減)するなら、次の世代は25%(0.5☓0.5)、その次の世代は12.5%(0.5☓0.5☓0.5)となり、三世代で出生可能年齢の女性が現状の10分の1近くまで縮小、人口減少に歯止めが掛からなくなるという実に素朴な理由でしかない。うるさいことをいえば、理論的には女子人口の規模がどんなに小さくなろうと純移動率(転出入の差)がプラスに転じ、合計特殊出生率が置換水準の2.08人を回復すれば、人口はいずれ下げ止まり、状況がさらに良くなれば増加に転じる(マルサスのいう通り、人口現象の凄いところはその指数関数的増加にある)。また自治体としての市町村が消滅を余儀なくされるかどうかは地方自治制度の問題であり、ドイツでは人口 8 名のミニ自治体もあるそう 5)で、何もかも人口のせいにされては困るというのが人口学者の立場だ。
しかし、現状のまま推移すれば進学・就職移動にともなう恒常的流出と、少子高齢化の帰結として始まった自然減の相乗効果から、市町村の人口減少が全国平均よりも遥かに急速に進み、遠からず多くの地域社会で持続可能性が失われるという結論自体に間違いはない。すでに2013年に国立社会保障・人口問題研究所の地域人口推計が出た段階でそれは明らかであったし、遡ればその初めて市町村別推計が公表された時から基本的状況に変化はない。私自身も論文・著作・講演などで繰り返し警告してきたが、遺憾ながら力及ばす日本創成会議ほどには一般の関心を喚起するに至らなかった。
この「消滅論」のユニークな点は、地方の人口減少の背景をなす、若年人口の流出と少子化問題を、首都圏という低出生力地域への一極集中という漠然した不安と結びつけた点にあり、この流れを断ち切らない限り、地域人口の再生はもとより、日本全体の人口減少も収束しえないと主張した点にある。文化勲章を受賞された高名な歴史人口学者の「大都市蟻地獄説」6)を持ち出したり、「極点社会」4)という奇異な概念については異論がある。また首都圏地域と地方の出生力格差や女子人口の不均衡分布だけでは、日本全体の超低出生力は説明できない。さらに進学・就職という移動要因から考えても地域からの人口流出は女子より男子の方が大きいなど随所に疑問は残るが全く間違っているわけではなく、誤解を含め、なまじの正統な理論より遥かに大きな政策的インパクトを持ったことは認めねばならない。
ただ、この政策の成否を考えた場合、気になるのが首都圏(あるいは大都市)と地方の結婚・出生力格差がどれくらいあるのか?それは何に起因しており、もし仮に一極集中が解消されるとすれば、日本全体の結婚・出生にどの程度の効果をもたらすのかという問題である。
これらの疑問に応えるには両地域の格差を具体的な指標により捉える必要がある。そこで2010年の人口動態統計の初婚件数と出生数、国勢調査の配偶関係別人口を利用し、全国(都道府県)、大都市部(東京特別区+政令指定都市)、地方部(それ以外)の3区分で、5歳階級別初婚率、未婚初婚率、出生率を求めて分析した。その結果、確かに都市と地方の間には結婚・出生力格差(表1)が認められたが、直近の状況をみる限り、格差は極めて限定的であり、「地方創生」により大都市集中を排除し家族形成期の若い人口をすべて地方に集めた(あるいは何らかの施策により大都市部の出生力を地方の水準まで上昇させた)としても、日本全体の合計(特殊)出生率を押し上げる効果は最大0.06程度しか期待できないことがわかる。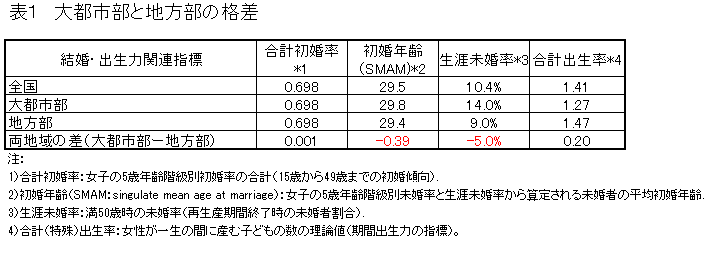
ちなみに女子の大学等進学率と上記3つの指標の相関関係をみると、いずれも20代の初婚率や出生率に強い負の影響を、また30代以降では正の影響を与えていることがわかった。いずれも、その傾向は大都市部で顕著であり、一般に大学等進学率の高い地域では、進学にともなう移動また在学中や卒業後間の時間が短いこともあり、20代で結婚・出産する可能性が低いこと、遅れた結婚・出産のキャッチアップから逆に30代以降で可能性が高くなると考えられる。事実、高年齢の35-39歳の出生率は大都市部の方が地方部より僅かに高い。つまり大学進学率の高低という観点からは、大都市部への人口集中が日本全体の出生力を低下させているという日本創生会議の主張は否定できない。
現状のわずかな出生力格差から考え、出生力への直接的効果は殆ど期待できないが、その一方、仮に「地方創生」により大都市集中を排除し家族形成期の若い人口をすべて地方に集めたとして、その場合の総出生数を試算すると、2010年の総出生数で年間約4万人、率にして3.7%多くなる。逆に、現状のまま一極集中が進み、全国が大都市化すると年間で約8.7万人、率にして -8.1%、少なくなる(表2)。興味深いのは、全国を地方化(あるいは大都市部の出生力が地方水準まで上昇)すれば、30-34歳以下のすべての年齢層で出生数が増えるが、35~39歳以上の高年齢層では減少する点であり、現状の大都市地域への女性人口の集中傾向が解消すれば、晩婚・晩産化に歯止めがかかることが示唆している。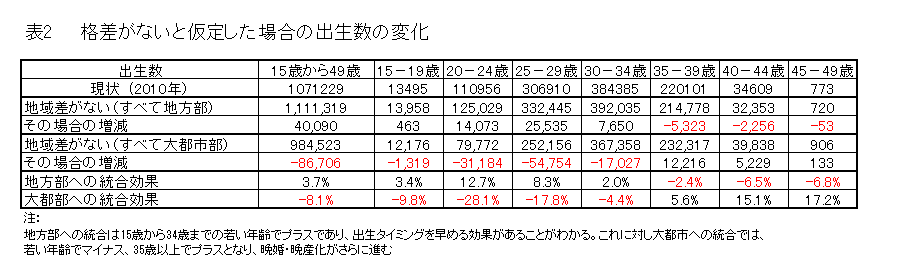
地方創生法施行とともに決定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン、総合戦略」では、希望子ども数の実現により全国の出生力を1.8程度に向上させ、2060年に1億人程度の人口を確保する、そのためには2040年頃までに出生力を置換水準の2.08まで回復するという形で、国全体としての人口ビジョンと実現のための総合戦略が打ち出されている。
現在、市町村で策定が進められている計画は、その地方版であるが、上記の試算によれば、2010年現在の出生力水準は全国1.41、大都市部1.27、地方部1.47であり、大都市と地方の格差は0.2程度しかない。このため、地方部でも1.80に遠く及ばない地域が大部分であり、また子どもの絶対数の減少もあり、すでに保育所の充実等も進み、財政的に可能な範囲で、できることはすでにやったというところも多い。また札幌のような大都市では独自調査の結果、希望子ども数そのものが1.8に達しないところもあり、出生力水準の目標設定に苦慮している。すでに多くの識者により指摘されているように、現状の低出生力は主として晩婚・晩産化によるものであり、大学等進学率の上昇による教育期間の延伸や人口の大都市集中を反映したものである。そうであるとすれば財政的制約からも地域レベルでの対応には限界がある。このため多くの自治体では出生力目標には素直に国全体の人口ビジョンの希望子ども数1.8(国の施策に他力本願的に敬意を払い)を想定、独自の両立支援や家族支援策では追加出生の増加より、むしろ家族形成期人口の転入増加をめざし、大都市部や近隣地域に対し、競争的優位性を確保する方向に進んでおり、その代わり、人口移動については転出超過を 0 あるいは転入超過に転じることで、人口減少を緩和または収束させることが目指されている。実際、多くの市町村では出生力の上昇効果より、純移動率の改善効果の方が大きく、この目標の方が遥かに現実的である。
地方の人口流出は進学・就職移動が中心であり、女性もさることながら男性の方が流出率は高い。実際、大学・専門学校はおろか地元高校や小中学校も廃校が進む中、若者の大都市への進学流出を止めることは難しいが、家族形成期の人口をUターンさせるか、新たにIターンとして大都市部から呼び戻すことは原理的に可能である。そのためには地方の競争的優位(夢と可能性を保障する就業機会、快適な住環境、豊かな自然、温かい人間関係)を創出する必要がある。とりわけ「20~39歳女性」の移動のかなりの部分が結婚によるものであることを考えれば、地方における、若年男性の就業機会創出が政策の鍵を握る。
いずれにせよ「地方創生」で「20~39歳女性」を一世代(約30年)で半減させる、現在の「地方消滅」への動きを止めるには、個々の市町村や地方だけの力では無理がある。すなわち希望子ども数1.8を実現するには、国政レベルの大胆な少子化対策支援策(たとえば、北欧並みの両立支援やフランス並みの家族支援を地方で実施できるようにする)が必要である。また地方と大都市地域間の人口再配置、経済格差の是正を画期的に進める国土開発(首都の複数化または首都機能や中央省庁の分散)や、産業移転・創出(金融機関はもとより本社・産業の地方移転・新規立地、雇用創出を条件とした法人税率の減免)などの国家的支援も不可欠であろう。最新の情報技術環境やエアラインの発達、さらには震災対策、安全保障なども考慮すれば、「地方創生」は十分可能であり、国家的選択としても必然性のあるものであると考える。その意味で新たに打ち出された「一億総活躍社会の実現」が「地方創生」に対する抜本的支援となることを期待して止まない。
<参考文献> ※ 文中の片括弧番号は、以下の文献の番号を示している。
1.日本創成会議(2015)「日本創成会議・人口減少問題検討分科会提言『ストップ少子化・地方元気戦略』記者会見」(http://www.policycouncil.jp)。
2.「まち・ひと・しごと創生法」。
3.首相官邸(2015)「まち・ひと・しごと創生本部」(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/chihou_sousei/index.html)。
4.増田寛也 編(2014)『地方消滅東京一極集中が招く人口急減』中央公論新書。
5.片木淳(2012)『日独比較研究 市町村合併 ― 平成の大合併はなぜ進展したか』早稲田大学学術叢書、175-182頁。
6.速水融(2001)『歴史人口学で見た日本』文春新書。